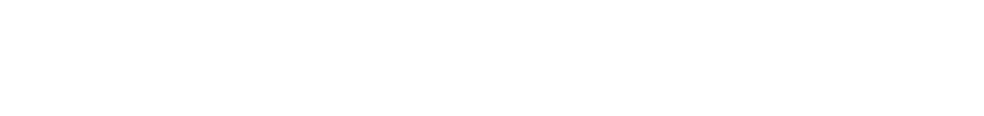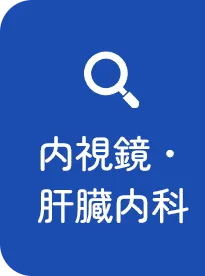インスリン製剤の種類と使い方

「インスリン治療は糖尿病治療の最後の砦」、「一度インスリンを使い始めたら止められないのでは」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、インスリンは糖尿病を治療する上で重要な薬剤であり、必要な場面で必要な量を使うことが大切です。
こちらのページではインスリンの種類、使い方、注意点などについて解説します。
インスリン製剤の種類と特徴
インスリン製剤は、作用発現時間(注射してから効果が表れるまでの時間)や作用持続時間(効果が続く時間)により分類されます。
糖尿病の状態に応じて、1種類もしくは2種類を組み合わせて使います。
ここでは、代表的な6種類のインスリン製剤をご紹介します。
① 超速効型インスリン製剤
食事の直前に注射することで、食事による血糖の上昇を抑えることができます。
これまでは、リスプロ(ヒューマログ)、アスパルト(ノボラピッド)、グルリジン(アピドラ)が使用されてきました。
2020年には、より作用発現までの時間が短いルムジェブ、フィアスプも使用可能となり、治療の選択肢がさらに広がっています。
- 作用開始:10〜20分
- ピーク:1時間前後
- 持続時間:3〜5時間
② 速効型インスリン製剤
超速効型インスリン製剤が登場する以前は、食事による血糖上昇を抑えるために使用されていました。
現在使用可能なものは、ノボリンR、ヒューマリンRの2製剤です。
インスリン抗体が陽性の場合や、ステロイドによる血糖上昇を抑えたい場合などに、超速効型インスリンの代わりとして使われることがあります。
- 作用開始:30〜60分
- ピーク:2〜3時間
- 持続時間:5〜7時間
③ 中間型インスリン製剤
速効型インスリンにプロタミンを添加して作用時間を長くしたインスリンです。
現在使用可能なものは、ノボリンN、ヒューマリンNの2製剤です。
- 作用開始:1〜2時間
- ピーク:4〜12時間
- 持続時間:12〜24時間
④ 持効型溶解インスリン製剤
約24時間以上持続し、夜間も含めて全体の血糖値を下げるためのインスリンです。
これまでは注射の回数が1日1~2回のデテミル(レベミル)、デグルテクトレシーバ、グラルギンが使用可能でした。
2025年に注射の回数が1週間に1回のインスリンイコデグ(アウィクリ)が使用可能となり、治療の選択肢が広がっています。
- 作用開始:1〜2時間
- ピーク:ほぼなし
- 持続時間:24時間以上(特にデグルデクは最大42時間)
⑤ 混合型インスリン製剤
速効型インスリンもしくは超速効型インスリンと中間型インスリンを一定の比率で混合した製剤です。
2種類の製剤が含まれているため、1日2回の投与で食事による血糖上昇と空腹時の血糖上昇の両方を抑えることができます。
⑥ 配合溶解インスリン製剤
超速効型インスリンと持効型溶解インスリンを一定の割合で混合した製剤です。
混合型インスリンと同様に、1日2回の投与で食事による血糖上昇と空腹時の血糖上昇の両方を抑えることができます。
どのような場面でインスリンを使うのか
糖尿病の薬物療法でインスリンを使うかどうかは、糖尿病の型・インスリン分泌の程度・合併症の状況などを踏まえて総合的に判断していきます。
インスリンによる血糖コントロールが必要となる場面は次の通りです。
①インスリン療法の絶対適応
以下のような状況では、インスリンを使うことが望ましいとされています。
- 1型糖尿病や、インスリン分泌が低下している2型糖尿病
- 糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖に由来する昏睡
- 重度の肝障害・腎障害・感染症
- 妊娠中もしくは、妊娠を計画している場合
②インスリン療法の相対適応
以下のような状況では、インスリンを使った方がよいとされています。
- インスリン分泌が保たれていても著明な高血糖を認める場合
- 経口血糖降下薬のみでは血糖コントロール目標が達成できない場合
- ステロイド治療を行っている場合
インスリンを使う上での注意点
インスリンを安全に使っていくために、以下のような点に注意しましょう。
低血糖
注射量と、食事や運動量が見合っていないときには低血糖を起こすことがあります。ブドウ糖や低血糖時の補食を常に摂れるようにしておきましょう。第三者の助けが必要な重症低血糖を引き起こす可能性もあります。家族や職場の人にも低血糖の時の対応を予め伝えておくようにしましょう。
シックデイの時の対応
体調が悪いときや食事がとれないときは、使っているインスリンの種類によってインスリンを続けるか、中止するかが変わります。主治医にあらかじめ対応を確認しておきましょう。
著者
この記事の監修者
糖尿病・内分泌・生活習慣病内科 金子千束 医師
糖尿病や内分泌疾患の診療を専門とし、患者さんの生活に寄り添った治療を心がけています。適切な治療により体調が改善し、生活の質が向上した多くの患者さんを拝見してきました。皆さんの生活がより健やかになるよう、一緒に考えていきたいと思います。
プロフィール
- 出身:茨城県(東京都育ち)
- 専門分野:糖尿病・内分泌疾患・生活習慣病
- 趣味:カフェ巡り、旅行、英語絵本多読
主な経歴
- 2009年3月 千葉大学医学部医学科 卒業
- 2009年4月〜2011年3月 関東中央病院 初期臨床研修医
- 2011年4月〜2015年3月 公立昭和病院 代謝内分泌内科 後期臨床研修医
- 2016年1月〜2019年3月 金沢赤十字病院 内科
- 2019年5月〜2025年3月 公立昭和病院 糖尿病・内分泌内科(2020年4月より医長)
- 2025年4月~ さいたま胃腸内視鏡と肝臓のクリニック和光市駅前院 糖尿病内分泌内科専門外来
専門資格
- ✓ 日本内科学会 総合内科専門医
- ✓ 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
- ✓ 日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医
- ✓ 日本専門医機構 内分泌代謝・糖尿病内科 領域指導医