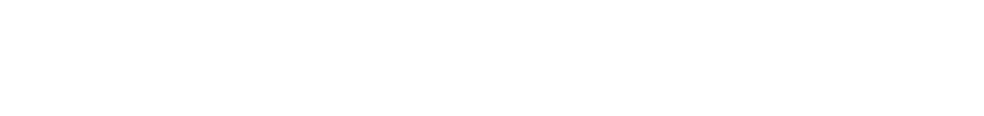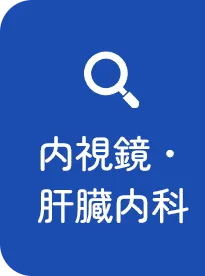なぜ体重管理が必要なの?
皆さんは、体重をどのくらいの頻度で測っていますか?
今回は、体重管理がなぜ大切なのか、目標となる体重の考え方、そして肥満と肥満症の違いについてご紹介します。
普段の診察では、体重管理の指標としてBMIがよく使われています。
▼BMIの計算式
体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
日本人では、BMI 18.5未満が「低体重」、25以上が「肥満」、22が「標準体重」とされています。
ただし、「肥満=すぐに病気」ではありません。
肥満が原因もしくは関係して、減量が必要な病気がある場合に「肥満症」と診断されます。肥満症に含まれる主な病気は、以下のようなものがあります。
・耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常など)
・脂質異常症
・高血圧
・高尿酸血症・痛風
・冠動脈疾患
・脳梗塞・一過性脳虚血発作
・非アルコール性脂肪性肝疾患
・月経異常・女性不妊
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群
・運動器疾患(変形性関節症、変形性脊椎症)
・肥満関連腎臓病
肥満症は、治療の対象となる疾患です。体重管理は、こうした病気の予防・改善につながります。
まずは、体重を測る習慣をつけることから始めてみましょう。体重は1日の中でも変動しますので、朝起きて排尿を済ませた後に測るのがお勧めです。
また健診で「血糖値が高い」「血圧が高め」などの指摘を受けた方も、体重との関係があるかもしれません。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。当院では、1人ひとりの状態にあわせて、無理のない改善方法をご提案しています。
この記事の監修者
糖尿病・内分泌・生活習慣病内科 金子千束 医師
糖尿病や内分泌疾患の診療を専門とし、患者さんの生活に寄り添った治療を心がけています。適切な治療により体調が改善し、生活の質が向上した多くの患者さんを拝見してきました。皆さんの生活がより健やかになるよう、一緒に考えていきたいと思います。
プロフィール
- 出身:茨城県(東京都育ち)
- 専門分野:糖尿病・内分泌疾患・生活習慣病
- 趣味:カフェ巡り、旅行、英語絵本多読
主な経歴
- 2009年3月 千葉大学医学部医学科 卒業
- 2009年4月〜2011年3月 関東中央病院 初期臨床研修医
- 2011年4月〜2015年3月 公立昭和病院 代謝内分泌内科 後期臨床研修医
- 2016年1月〜2019年3月 金沢赤十字病院 内科
- 2019年5月〜2025年3月 公立昭和病院 糖尿病・内分泌内科(2020年4月より医長)
- 2025年4月~ さいたま胃腸内視鏡と肝臓のクリニック和光市駅前院 糖尿病内分泌内科専門外来
専門資格
- ✓ 日本内科学会 総合内科専門医
- ✓ 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
- ✓ 日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医
- ✓ 日本専門医機構 内分泌代謝・糖尿病内科 領域指導医
この記事の監修者
吉良 文孝 医師
さいたま胃腸内視鏡と肝臓のクリニック和光市駅前院 理事長
主な経歴
- 平成15年:東京慈恵会医科大学 卒業
- 平成15年:東京警察病院 勤務
- 平成23年:JCHO東京新宿メディカルセンター 勤務
- 平成29年:株式会社サイキンソー CMEO 就任
- 平成30年:東長崎駅前内科クリニック 開院
- 令和3年:さいたま胃腸内視鏡と肝臓のクリニック和光市駅前院 開院
専門資格
- 日本内科学会 認定内科医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 内視鏡専門医
- 日本肝臓学会 肝臓専門医
- 日本糖尿病学会 会員
- 日本抗加齢学会 会員